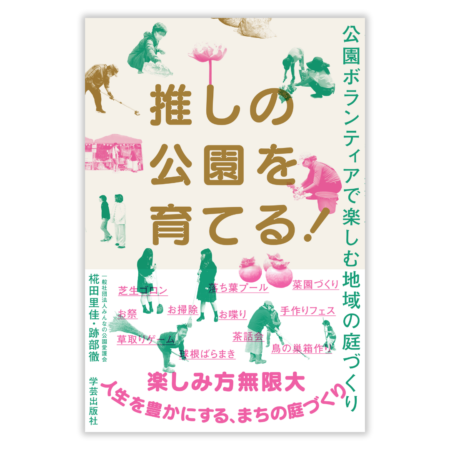大阪公立大学の学生が、大阪市の公園愛護会の皆さんの活動を紹介する「大阪となりの公園愛護会」。公園の利活用やランドスケープ設計を学び研究する学生の視点で、公園ボランティア活動を紹介します。
今回は大阪市西区の九条南公園(くじょうみなみこうえん)愛護会。みんなの公園をみんなできれいにする意識が浸透して習慣になっている美化活動のお手本のような公園を取材してきました。
公園愛護会と町会女性部が役割分担で公園美化
阪神九条駅/大阪メトロ九条駅から徒歩5分程度の少し懐かしさを感じさせる住宅街に位置する九条南公園。目の前には大阪市立九条南小学校があり、放課後に遊ぶにはぴったりの、まさに子どものための公園です。
ここでは、九条南連合の南二(なんに)町会の方を中心とした公園愛護会が、毎月第1日曜日の朝の7時から公園内の清掃を1時間、九条南連合の女性部が公園周囲の溝の清掃を1時間ずつ活動するスタイルをとっています。九条南連合の女性部は町内の溝を全体的にきれいにしているそうです。九条南公園周辺の溝はその一環なのですね。
九条南公園愛護会副会長の渕野さんと女性部長の濵垣一美さんをはじめ、メンバーのみなさんにお話をお聞きしました。

取材日は8時に訪問したため、公園愛護会の活動は終了していました。そのため女性会の活動のようすの写真を少しだけですが掲載します。
取材した6月は落ち葉が比較的少ないですが、排水口の周りなどはやはり細かなものが溜まりやすく、丁寧にごみを集めていました。

活動を終えて少し立ち話をしていた愛護会メンバーの方にお話を聞いてみたところ、この日のごみは量が少なかったそうです。秋冬になると落ち葉が多くあったり、春には桜の花びらがあったりと清掃に多くの時間を取られてあまり除草に手が回らないとのことでした。
朝早くの活動ではありますが、朝なら涼しいうちに活動ができて、活動後の予定も組みやすいと教えてくださいました。
小学校が隣にあるということもあり、お話をしてくださったメンバーの方は「子どものためにやっている」「草を刈ったりきれいにして、公園で子どもが遊んでくれると嬉しい」など子どもに関する話題がたくさん出てきました。
取材中は朝が早かったからか子どもが遊んでいるようすはありませんでしたが、公園内の砂場やグラウンドの部分から子どもがたくさん遊んでいる場所の痕跡が見つかるような、人の気配を感じる公園でした。

みんなの草刈りリーダー!
九条南公園愛護会副会長の渕野さんは、毎日公園清掃をされています。また、公園全体の草刈りについても主体的に考え実施されています。毎日少しずつ草刈りをして、1mほどの背丈のあった雑草を短くして見通しのいい公園にしています。この日も朝6時半から草刈りをされていました。
取材日の4日後に、九条南小学校の児童による公園の清掃行事があるため、児童が公園の隅々まで入っていけるようにとの気遣いから草を刈ったそうです。きっと児童は公園中を駆け回りながら楽しくごみ拾いをしてくれたことでしょう。
この公園には花壇はありませんが、現在は勝手に生えてきたお花を大事にとっておいているそうです。取材日はちょうどきれいに咲いている時期でした。

京セラドームがあることでも知られる大阪市西区ですが、ここは一人暮らし向けの賃貸マンションが大阪市内でも比較的多く存在します。九条南公園の近くにも単身赴任者向けマンションがあり、毎朝九条南公園の横の道を通る一人暮らしの方が、渕野さんが毎朝公園に来て清掃や草刈りをするようすを見て活動に興味を持ち、話しかけられたことがあるそうです。愛護会の活動を紹介したところ、ちょうどこの日の活動に参加されていたそう。なんと東北地方の出身だとか!見知らぬ土地で地域コミュニティ活動に参加することのハードルは高そうですが、勇気を出して活動に参加されたのでしょうか。こうして活動の輪が広がっていくのだろうな、と感動しました。
私自身も一人暮らしの経験がありますが、一人暮らしをしている人は地域に関わりを持つことが少なく、特に賃貸では自治会にも入らないため、地縁団体に関わるきっかけも実際の関わりもないことが多くなりがちです。公園での活動が地域とつながるきっかけになるというのはとても素敵ですね。
活動後は、つながりを育むモーニングで交流
さて、九条南公園愛護会の会長さん、大杉壽男さんに伺ったお話に至るまでが非常に長くなってしまいました。大杉さんは南二(なんに)町会の会長を兼任しており、九条南公園からほど近い場所にあるcoffee&snack CHAPLINをご夫婦で営んでいます。南二とは、九条南2町会の略称だと教えていただきました。おいしいモーニングをいただきながらお話を伺いました。大杉さんのエプロンについているは虫類に似たようなかわいらしい生きものがとても印象的です。

活動終了後は女性部の方を交えてこのカフェでモーニングをいただきながらおしゃべりをするのが恒例になっているそうです。なんて優雅で素敵な朝活なんでしょうか。カフェでは女性部の皆さんにたくさんお話をしていただきました。

まずは、九条南民生委員長もされている仁熊育代さん。児童委員をしていたときに地域の子育てサロンに来ていた子どもが大学生になってお母さまと一緒に公園愛護会活動に参加してくれたことがあったそうです!子どもの頃に見守っていた子が大きくなっていたことはもちろん、地域への恩返しのためにと参加してくれたことが嬉しかったことを話してくださいました。
女性部の皆さんと、「地域のことが回り回って子どもにも伝わっていることが素敵!」「繋がりができていくのがいいことですね!」など感激しながらこの素敵なエピソードだけで10分以上話し込んでしまいました。かつての少年が地域に参加する立派な青年になったように、次の世代に地域のことが引き継がれていくようすを実感できることが地域コミュニティ活動の醍醐味の一つかもしれません。
あとがき
一人暮らしの方が参加したり、かつての少年が清掃活動にご家族で参加してみたりと、公園ボランティア活動が地域のコミュニティに繋がっているというお話をたくさん聞く事ができ、感動続きの取材でした。
公園の清掃や除草は傍から見ると小さな活動かもしれないけれど、その裏にある一人ひとりのことを知ると、地域に輪が広がっていく実感を得ることができ、充実した活動をされていることがわかります。特に大人になって地域に恩返しをする、というお話は私の世代と近い方のエピソードであることもあって、私も何か地元に還元できることはないかと探したくなりました。
【基本情報】
| 団体名 | 九条南公園愛護会 |
| 公園名 | 九条南公園 (大阪市西区) |
| 面積 | 3809 m2 |
| 基本的な活動日 | 毎月第1日曜日7:00~ |
| いつもの活動参加人数 | 10人程度 |
| 活動内容 | ごみ拾い、除草、落ち葉かき、低木の管理、花壇の管理、植物の水やり、施設の破損連絡、利用者へのマナー喚起、愛護会活動のPR、新メンバーの募集や勧誘、地域のイベント、子ども向けイベント、他団体と連携したイベント、遊びの見守り、高齢者など地域の声がけ |
| 設立時期 | 1965年4月 |
| 主な参加者 | 地域(南二)のボランティア、アクティブシニア |
| 活動に参加したい場合は | 活動日にお越しください! |