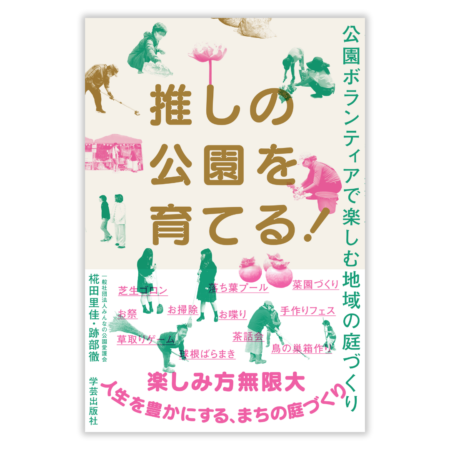さまざまな公園育て活動を紹介する「となりの公園愛護会」。大阪公立大学の大学生が、公園の利活用やランドスケープ設計を学び研究する学生の視点で、公園ボランティア活動を紹介します。
今回は、初の大阪府堺市の公園愛護会です。7月にみんなの公園愛護会代表の椛田が参加した堺市公園愛護会研修会で、活動発表とパネルディスカッションの登壇をされた吉田美津江さんが活動する、土師町ちどり公園(はぜちょうちどりこうえん)にお伺いしました。
研修会での活動発表をきっかけに、市内各地から見学者が!
吉田さんはご自宅のすぐそばにある土師町ちどり公園で多くのお花を管理して活動されています。7月の公園愛護会研修会では、普段の活動の様子として「まるで自分の庭のように公園の花壇を手入れし、近隣の方にも楽しんでもらっている」という発表をされました。筆者も研修会に参加しましたが、とても活動を楽しんでいるというのが発表の話しぶりから伝わってきてその姿がキラキラして見えました。
吉田さんは、15年ほど土師町ちどり公園での活動を行ってきて、ご自分のしていることを発表する機会があったことで、人知れずやってきたことや、それを通した公園の変化を知ってもらえたことがよかったとのことでした。
なんと研修会のあと、他の公園愛護会の方々から土師町ちどり公園を見学したいという希望があったのだそうです。わざわざ何キロも離れた場所から自転車で見学に来た公園愛護活動者もいらっしゃったそうで、吉田さんの活動と公園の魅力が他の活動者の心を動かしたことがわかります。

もともと吉田さんもきれいに育って咲いているお花を多くの人に見てほしいと思っていたそうで、こうしてたくさんの人に見てもらえるきっかけになったことをとても喜んでいました。
今回の取材は秋から冬になる時期だったのですが、春にお花畑のようになっている様子もぜひ見てほしい!と写真をいただいています。特にそのシーズンで初めて咲く瞬間は嬉しいそうです。咲き乱れる花々の写真を見ていると、ぜひ春に訪問して実物を見てみたくなります。

秋冬でもお花はたくさん!春に向けての準備も
今回は、堺市公園協会の鈴木美穂さんと山本将大さんも来てくださり、堺市公園協会の取り組みでもある職員と公園愛護会の共同作業の様子も見学しました。この日は春先に咲く花の球根や苗を植える作業をご一緒に。鈴木さんや山本さんに、「三角をイメージして植えるときれいに見えますよ!」と花壇づくりのコツを教えながら、和やかな雰囲気で植付けが終了。今から春が楽しみです。

この花壇は、堺市の制度「パートナーシップ花壇」として登録されたものであり、以前の公園愛護会員から公園愛護活動を引き継いだ吉田さんがご自身で登録をしたそうです。吉田さんは、堺市の花のボランティア活動「花いっぱいゃさかい」の会員としても活動されていました。花いっぱいゃさかいは、種から花苗を育てる「花づくり」、花苗を植える「花かざり」、水やりなどの世話を行う「花守(も)り」の3つの活動を行っています。市内の圃場で花いっぱいゃさかいの会員が育てた花苗は各地のパートナーシップ花壇に提供されています。
ご自宅ではなかなかお花をたくさん育てることができなかった吉田さんは、こうして公園の花壇でたくさんのお花をお手入れすることで園芸を楽しんでいます。
ニゲラやピンクパンサーは種から発芽したものをそのまま育てていたり、マーガレットは挿し芽をすることで増やしたりしているそうです!挿し芽から育てるのは高い技術が必要なイメージだったので、案外簡単にできると聞いて驚きました。

厚手の上着が必須の時期に取材をしたにも関わらず、公園には所狭しとたくさんのお花が咲いていました。その種類ごとに名札を立て、お花の知識がまだ浅い私のような人でも楽しめるように工夫されています。これらのお花は堺市公園愛護会の補助制度である協力金で購入したり、同じ堺市内にある大仙公園の緑化センターの廃棄植物をもらってきたりして入手したとのこと。

吉田さんはこれまで、公園を彩るお花に加えて、ホースや芝刈機、種、苗なども協力金で購入してこられたそうです。
しかし、近年お花は価格の高騰により以前のように購入しづらい状況になっていることや、今後は協力金の使い道を土や肥料に変更することを検討したいというお話もしてくださいました。
きれいなお花を咲かせるには土づくりも欠かせないので、使えるお金が限られる中で工夫しながら花壇づくりを楽しんでいるのですね。必要に応じて適切なものを購入できるのは、日頃から公園を見ていてこそできることでしょう。

今はこんなにきれいな公園も、荒んだ過去がありました
今でこそお花にあふれたきれいな土師町ちどり公園ですが、吉田さんが引っ越してきたばかりのおよそ20年前は、ここは砂場にガラス片やタバコの吸い殻などが散乱し、荒れた少年らの隠れ家的な場になるなど荒んだ状態にありました。学校や警察に通報して対応してもらうようなこともしばしばあったそうです。
花のボランティア活動に参加するようになった吉田さんが公園愛護活動を引き継いでから、根気強く砂場を掃除し、花を植え、公園をきれいに保つことで徐々にそのようなことは減っていきました。その後、小さな子どもが安心して砂場遊びをしたり、近隣の方がお花を鑑賞する場になったそうです。1人の行動が、近寄りがたい公園を愛される公園に変えたというなんともドラマのようなお話です。
また、過去にはアリやナメクジが多く生息し、カラスがよくやって来ていた土師町ちどり公園ですが、活動を続けるとトカゲやバッタが増加し、チョウがやって来たり、イソヒヨドリが飛来するようになったそうです。水栓があるため蚊がなかなか減らないことが最近の悩みなのだそう。活動を通じた変化は動物にもわかるものなのですね。
こうして素敵に生まれ変わった土師町ちどり公園。少し奥まったところにありますが、一歩入ると案外広く常にお花がきれいに咲いているので休憩にはぴったりです。「より多くのご近所さんがお花を見にきてくれるとうれしいですね。」と話してくださいました。


公園を1人でここまで管理するというのはとても大変そうですが、そのことについて吉田さんは「家のそばに公園があったからできた」と振り返ります。もし1キロ先に公園があったらこれだけの活動はできなかった、とも。すぐに行ける距離だからこそ手間をかけてあげられたのですね。
現在、吉田さんは公園での花育てに加えてご自宅で育てたお花を近隣に配るなど、お花を育てる活動を通して地域との交流を強めています。高齢の方が多く住んでいるとのことで、ご近所さんへの声かけにもなっているのだそうです。
ご近所さんからも現在の土師町ちどり公園は好評で、近くに住んでいる方から吉田さんに電話があり、「この公園は地域の誇りや!」と褒めていただいたことを嬉しそうに教えてくださいました。また、取材中にはお隣の方が公園の様子を覗きにやって来て、「いつも楽しませてもらっています」とおっしゃっていました。

これからの活動も考えています
「公園のおかげで元気にやれている」と話す吉田さん。コロナ禍でもお花のお世話をするなど、公園でやることがあったから外に出てリフレッシュになったというお話をしてくださいました。
公園愛護会の活動は、愛護活動者が「やらされている」感覚になっているのはよくないとのこと。ボランティアはやらされている感覚があるとなかなかうまくいかないものなので、まさにその通りですね。今は1人で活動をされていますが、これからのことを考えると複数の人で公園のお手入れをすることも検討しているそうです。
しかし、「来てもらえたら助かるけど当番ができなかったら大変だし…」とお悩み中です。また、「やらされている人よりはやりたい人とがいい!」とのことでした。もしこの記事を見て土師町ちどり公園で活動をしたい方は堺市公園協会へぜひ連絡してみてくださいね!




【基本情報】
| 公園名 | 土師町ちどり公園 (堺市中区) |
| 面積 | 150 m2 |
| 基本的な活動日 | 日曜日 |
| 活動内容 | ゴミ拾い、除草、落ち葉かき、低木の管理、花壇の管理、植物の水やり、施設の破損連絡、愛護会活動のPR、新メンバーの募集や勧誘、遊びの見守り、高齢者など地域の声がけ |
| 設立時期 | 2008年 |
| 活動に参加したい場合は | 堺市公園協会へご連絡ください |