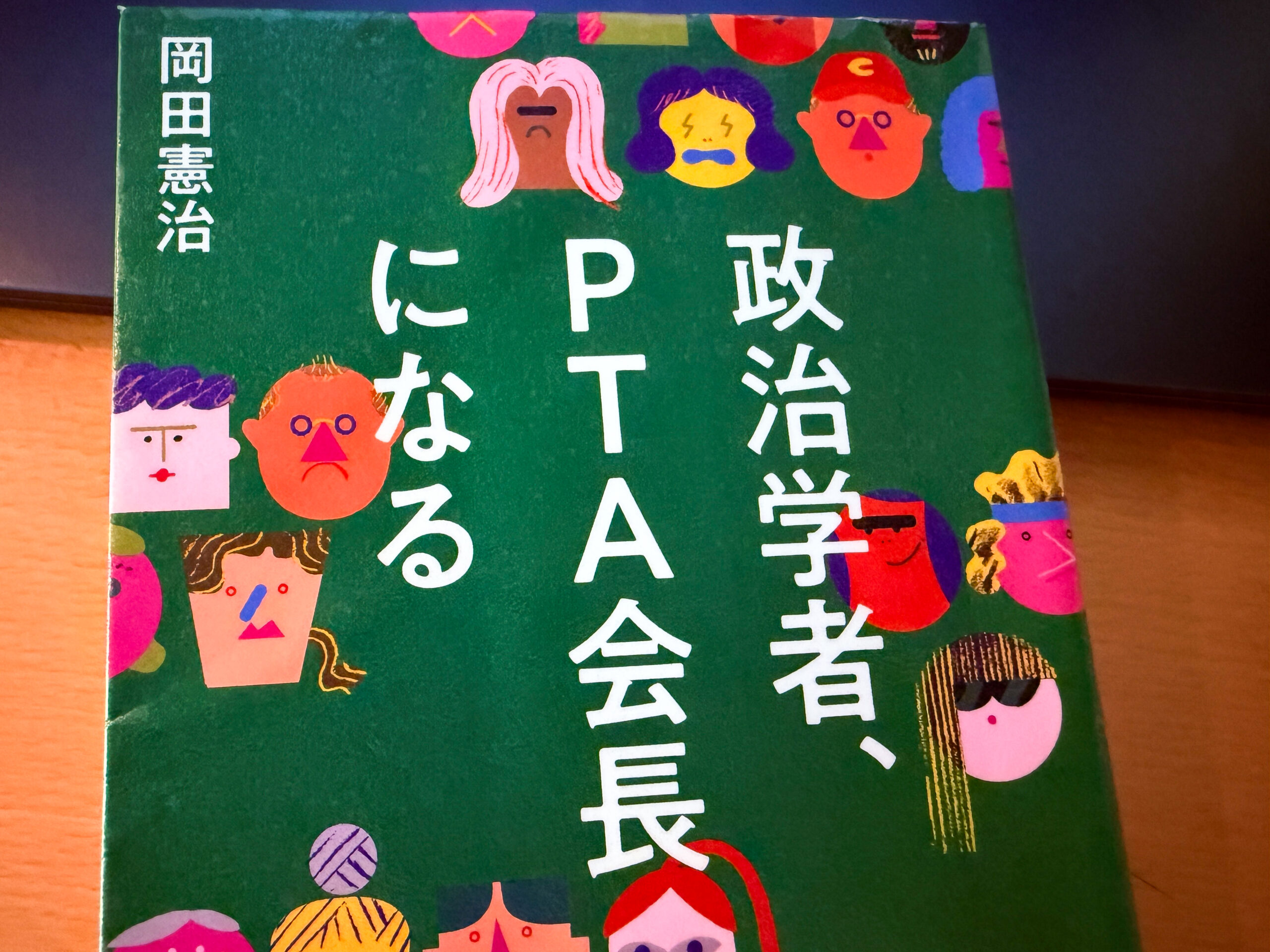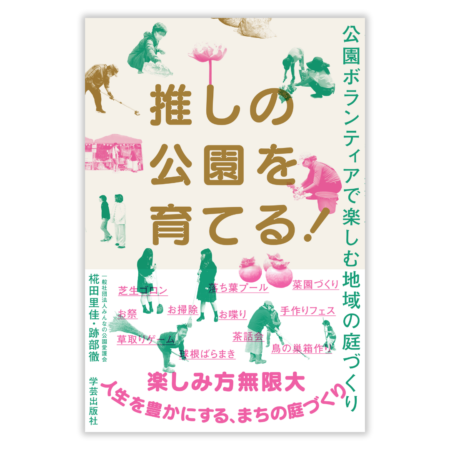こんにちは。みんなの公園愛護会理事の跡部です。
またまた、公園ボランティアの運営を考えるときに参考になる書籍を見つけました!
その本は、、、、岡田憲治著『政治学者、PTA会長になる』(毎日新聞出版)です。
以下の紹介文を読んでみてください。私は小学生男子二人の父親としてPTAのこととして読み始めたはずなのに、頭の中では「公園ボランティア」をイメージしながら読んでしまいました。
うっかり踏み込んだ先は「魔界」だった…
理論も“ご高説”も役立たず!?
実践・街場の民主主義1000日の記録小学生の保護者たちの胸をざわつかせる「PTA」の存在。
そんな場所にうっかり義憤に駆られて、政治学者が踏み込んだら……?
政治学の思考のフィルターを通して、PTAを見てみたら浮かび上がってきた、
「スリム化」を阻むものの正体、「やめよう! 」が言えない大人たち、
「廃止」が必ずしもベストではない事情……。
そして、コロナで学校が閉ざされた時、PTAが果たした役割とは?今の時代に合うPTAの形とは、続ける意味とは何か?
身近な自治の場「PTA」での著者の1000日を通じて考える、
私たちの「自治」の話。”
—
PTAも公園ボランティアもどちらもボランティア活動。
以下の文章も、ボランティア活動をしている人には、首を何度も縦にふって頷きが止まらなくなる文章ではないだろうか。
ボランティアとは、もともとは「求める」「欲する」という意味の「ウォロ」というラテン語から生まれた言葉だ。そこには「人と比べて」という発想はない。「あたしがやりたい、やってあげたい、やらずにいられない」からやる、というシンプルな前提があるだけだ。
他方、「平等」という考え方には、必ず何かを基準に他者と比べるという発想がある。「同じ労働をしているのにどうして女性の賃金は男性よりも低いのか?」というこの世の理不尽を訴える時には、平等とは、世界をきちんと正すために必要な言葉だ。
・・・
そして、そこに軸足が残ってしまうと、「負担とか、そういうことじゃなくてやってあげたい、その気持で活動できる幸せ」という、ボランティアの「一番ありがたい(滅多にない)ところ」が裏側に押しやられてしまう。そうなると、「平等だけどなんか辛い」、「公平負担なのに、サボってる人がムカつく」、「一人一役ったって、役員と古紙回収じゃ負担比べものになんないし」といった、正直でネガティブな気持ちが頭をもたげて、全体としての雰囲気が「結局やらされてる感」が基本のトーンのPTAとなってしまうわけだ。
・・・
だから、もしどうしても「平等」という言葉を使いたい人がいるならば、こう言い換えねばならない。
ボランティアはもともと不平等なものだよ。でも、それは「幸福な不平等」でしょう、と。
そしてこの本の素晴らしいのは、政治学者である筆者が「合理化、効率化」を念頭にPTA会長となるものの、いろいろな実体験を経て、何が大切なのかに気がついてく成長物語となっていることです。
「ここに居る人たちは、誰に強制されたわけでもなく、自ら進んでこの場に肉体と時間を提供している」という気付き。
最初は不満に思っていた活動も活動の現場をちゃんと見ること。悪意でそうなっているのではなく、すべて先人たちが苦労してやってきたこと。そこへ敬意と配慮が必要なこと。
例えば。係30人で4時間やってだいたい4000円の収益だったベルマーク活動を廃止しようと思っていたが、話を聞いたら、そこには効率では測れない価値があったという話。
「収益が上がっていないものを継続する必要なし」という100%企業ロジックの罠にひっかることもなく、本当に切実な、生活における意味あるPTA活動の機能を学んだのである。
これは公園ボランティアにおける除草作業と共通しています。草取りはもちろん大変で非効率で機械化するなど工夫がありますが、一方でプロセスとして草を取りながらおしゃべりをするという価値を忘れてはいけません。
大事だなぁと、しみじみ感じたのがお礼を口に出して述べること。現場で力を貸してくれる人は、みんなそれぞれの気持ちでやってくれている。少しでも隣人を助けようと工夫してやってくれている。だからこそ、お互いが気がついたときに「ありがとう」を言うこと。それが、力を出しやすい環境につながる。
巻末にあるPTA「思い出そう、十のこと」も最後に紹介します。公園ボランティアの運営に当てはまる部分もいっぱい!
1.PTAは、自発的に作られた「任意団体」です。強制があってはなりません。
2.PTAは、加入していない家庭の子供を差別しません。企業ではないからです。
3.PTAのに人が集まらないなら、集まった人たちでできることをするだけです。
4.PTAがするのは、「労働」ではありません。対価のないボランティア「活動」です。
5.PTAのボランティア活動は、もともと不平等なものです。でも「幸福な不平等」です。
6.PTA活動は、ダメ出しをされません。評価はたった一つ「ありがとう」です。
7.PTA活動は、生活の延長にあります。家庭を犠牲にする必要はありません。
8.PTA活動は、あまり頑張り過ぎてはいけません。前例となって「労働」を増やします。
9.PTAは、学校を応援しますが指導はされません。学校と保護者は対等です。
10.PTAの義務は一つだけです。「何のためのPTA?」と考え続けることです。
ぜひ、夏休みの課題図書としてこの本を手に取ってみてください。