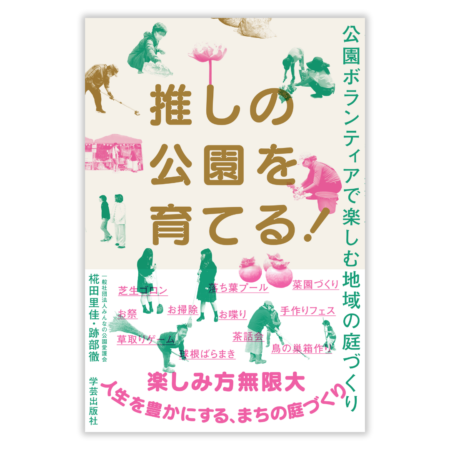公園ボランティアに関わるさまざまな人がその活動や思いを綴る「みんなの公園愛護活動 連載コラム」。神戸市長田区を中心に公園から面白いことを仕掛けて、まちづくり活動に広げているSoooGood ながた(ソーグッドナガタ)の西山泰さんの連載、第2回です。
川沿いの公園に、みんなでシェア畑をつくったことで、
「次は公園に何作ろう?」「もっと面白いことできるんちゃう?」と、
どんどんアイデアが広がっていきました。
もっと賑やかで、楽しい水辺ストリートにしたい──。
そんな思いと、たくさんの人との出会いから生まれたのが、神楽公園のバスケットコートづくりです。
今日はそのストーリーをお届けします。最後まで読んでいただけたらうれしいです。
なぜ公園にバスケットゴールを?
新湊川公園でコミュニティ菜園がスタートして、
「公園って、こんなに簡単に人とつながれる場所なんだ」と実感しました。
その時から、「次はもっといろんな世代が楽しめる場所をつくりたい」と思いはじめたんです。
畑を見渡すと、子どもや大人は集まってくるのに、中高生の姿があまりない。
SNSでバスケを楽しむ子どもたちの投稿を見た瞬間、「今の時代、やっぱりバスケやな」と感じ、
スリーオンスリーができるようなスペースを公園に作りたいと考えるようになりました。

出会いと共鳴:まちのデザイナーとの協働
そんなタイミングで参加した長田区役所主催の「長田ゼミ」で、
バスケゴールを増やしたいと語る若者に出会います。
プレゼンでは、「バスケットゴールがあると、友達が増える。男女関係なく遊べる」と、
まちに必要な理由が熱く語られていました。
その瞬間「うちの公園で一緒にやりませんか?」と即アプローチ。
思っていれば出会えるもんだなと感じました。

中高生たちのリアルな意見
次に、実際に使う子どもたちの声を聞くことにしました。
長田中学校や彩星工科高校の探究授業の中で、100名以上の生徒に「神楽公園にバスケットゴールがあったらどう思う?」と聞くと、ほとんどが大賛成。
「遊びたい!」「放課後行きたい!」というリアルな声がたくさん返ってきました。その後、キャッチボール交流会やごみ拾いも一緒にやりながら、少しずつ公園と中高生との距離が近づいていきました。


神戸市のバスケットゴール倍増計画
そんな中、神戸市にプロバスケチームが移転し、市が「バスケットゴール倍増計画」をスタート。
これまで少しずつ積み上げてきた僕たちの活動に、ようやく大きな追い風が吹きました。
高校生たちも「本当にできるんや!」とワクワクし、掃除や運営にもチャレンジ。
2年生の学生が会長となり、教員を含めた数名で、神戸初の高校生による公園管理会を結成しました。
神戸市の職員から制度について話を聞きに行き、最初はみんなちんぷんかんぷんでしたが、「やったらわかることもあるよ」と声をかけ、思い切ってスタートすることにしました。
その後は、デザイナーと一緒にコートの色を決めるワークショップも行い、
自分たちの公園を自分たちでつくるという実感が、少しずつ育っていきました。


地域全体でつくった空間
バスケットコート完成に向けたオープニングでは、学生たちが「ごちゃまぜスリーオンスリー大会」を企画。小学生から大学生、プロバスケ選手までが集まる夢のようなイベントになりました。
婦人会やPTAの方々も協力してくれて、「知らなかった人同士がつながる」瞬間があちこちに。
公園に何かが生まれると、人もまちも動き出すんだと改めて感じました。

課題と希望のあいだで
あれから1年。神楽公園は放課後の“たまり場”としてすっかり定着しました。
暑い日も寒い日も、誰かがいて、体を動かしている。そんな場所になっています。
一方で、人が増えたことでポイ捨てのゴミも目立つようになってきました。
高校生たちと「ゴミ箱をどう設置するか?」という議論も始まりました。
今年8月には神戸市の社会実験で自販機+ゴミ箱も設置予定。
“完璧”にはならないけど、みんなで話し合いながら育てていけたらと思っています。

つながり続ける公園の未来
つい最近、オープニングイベントで始球式をしてくれた子に、ふと公園で声をかけられました。
「また、あのイベントみたいなん、やろうや!」と、笑いながら。
バスケットゴールをきっかけに、こんなふうに声をかけ合える関係が生まれたことが、何よりの成果だと感じました。
そんな小さな声がまちを動かし、日常を少しずつ豊かにしていく。だからこそ、これからも焦らず、じっくり、みんなで育てていきたいと思っています。
公園は、可能性の宝庫です。